
地産池消の家づくり
木材は、構造材や造作材、化粧材など地元霧島地区の杉・桧を全面的に使用しています。 地元の気候・風土に適した木材でつくる家が地元には一番合っています。また住まいずの家は、普通ならベニヤか石膏ボードを使用するところ、押入れや クローゼットの中まで、本物の杉板を使用していますので、カビの発生を抑え、清潔さを保ちます。

自分の山の木でつくる家

お客様とともにつくる自然素材の住まい
かつて木・土・石・紙などを使って家を建てていた頃には、そうした問題は皆無でした。現在は国によって新建材にも化学物質使用の制限が加えられていますが、それよりも初めから自然素材を使った方が良いことは明らかですよね。
樹齢50年の木は、その生きてきた年数と同じだけ、家の材となってからも寿命を保つと言われます。きちんと手入れをしてやれば、もっと長生きします。そしてその間、湿気が多い季節は湿気を吸い、少ない季節は湿気を放出してくれるのです。梅雨時でも無垢の木の床はさらっとしているでしょう?あれがそうです。同様に漆喰の壁も調湿効果をもっています。
何より自然素材は心を落ち着かせます。自然を征服するべき相手と見なして来た西洋とは異なり、日本人は大昔から自然を母のように慕ってきました。障子、縁側、坪庭・・・・すべて自然と住まいを連続させるための工夫です。自然を感じて暮らしたいというのは、日本人の根源的な欲求。やはりそれを叶える家が住みやすい家なのではないでしょうか。

本物の木の家「五季の家」
国土交通省が推奨する長期優良住宅のモデルハウスです。かごしま材と地元の自然素材だけにこだわり、光と風を取り込んで、人と自然が共生して心からくつろげる「本物の木の家」です。夏には木陰の涼しさを、冬には陽だまりの暖かさを・・・森呼吸システム(二重通気工法)を採用、壁内の空気を循環することで室内で極端な温度差がなく、一年中快適に過ごせます。

一棟入魂 〜匠たちのプライド〜
木が好きで、木造りに喜びを感じ、プライドを持つ匠たちの手による気合の入った温もりの伝わる家づくりです。「一棟入魂式」住まいずでは、建築に入る前に関係者が一同に集まり皆の気持ちをひとつに「入魂式」を行ないます。施工期間中は互いに作業をチェックしあいながら、責任と誇りをもって完成させていきます。お施主様のお喜びの笑顔に出会うために。

ごあいさつ
家を建てようと思っている方はみなさん「良い家をたてたい!」と、理想を描くと思います。
では「良い家」ってどんな家でしょう?
夏でも冬でも過ごしやすい家、広々としたリビングがある家、最新の省エネ設備がついている家、耐震性が高い家など、
その人の価値観によっていろいろな「良い家」があると思いますが、その先には「幸せに暮らしたい」という思いが
含まれてるのではないでしょうか。
家を建てる目的は、「家」そのものではなく楽しく幸せに暮らすことではないでしょうか。
あくまで、家は幸せに暮らすための人生を楽しむためのツールなのです。
ツール(道具)だから、みんな大切にするし、磨きもする。
そして、私たちはそのより良い人生のためのツールをつくるお手伝いをしている感覚です。
だから家づくりを一緒に楽しみたいし、家が完成した後もお付き合いを続けていきたいのです。
弊社で家を建てた家族が笑顔で幸せに暮らしているのを見ることが、私たちが何よりのやりがいを感じられるときです。
家づくりを通して、幸せな家族が増えることが私たちの願いです。

鹿児島発、地産地消の家づくり
おばま工務店の家を見ていると、そんなイメージが湧いてくる。
生まれ育った街、住み慣れた土地は人に安らぎと温もりを与えてくれる。「かごしま材」に徹底してこだわっている。ただこだわるだけでなく、自分の山の木を持っているお客様がいれば、その木を使って家づくりをするのだ。
まさに地産地消。だからこそ建てた家には一層の愛着が湧き、完成した時の喜びも一入なのだろう。地元産材を使用することは、地元の山を守り、ひいては環境にやさしい循環型社会を形成していく。
”毎日を楽しく心地よく暮らす”ことを家づくりの基本にしているおばま工務店。その“心地よさ”は住む人のみならず、地球環境というもっと大きな世界を見据えているようだ。
基本情報
| 企業名 | おばま工務店/株式会社住まいず |
|---|---|
| 住所 |
〒899-5103 鹿児島県 霧島市 隼人町小浜28 |
| 施工エリア | 鹿児島県 |
| 設立年 | 1998年 |
| 資本金 | 300万円 |
| スタッフ数 | 16人 |
| テーマ |






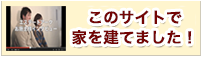
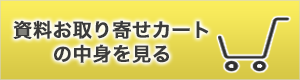

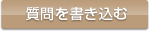




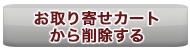

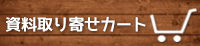
 エム・ハウス/株式会社小野瀬工務店
エム・ハウス/株式会社小野瀬工務店  株式会社ムサシノ建設
株式会社ムサシノ建設  有限会社 建築サポート
有限会社 建築サポート  おばま工務店/株式会社住まいず
おばま工務店/株式会社住まいず 